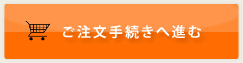書籍紹介「若返りホルモン」米井嘉一 著
「若返りホルモン」
米井嘉一 著 ISBN978-4-08-721278-5
健康診断や人間ドックでは、通常、測定されることのない血中ホルモン量が心身の老化と密接に関係している。長年、老化のメカニズムの研究と診断・治療に取り組み、患者の「若返り」を実証してきた抗加齢医学研究の第一人者である著者はそう明言する。
Ⅰ 機能年齢
肉体や臓器の機能面の老化は、個体差が非常に大きいという特徴がある。
1.5つの機能年齢
「ホルモン年齢」が最も重要なカギを握りほかの4つの機能年齢にも多大な影響を与える。
(1)「血管年齢」「筋肉年齢」「骨年齢」「神経年齢」「ホルモン年齢」
(2)ホルモンが作用する2つのルート
・「自律神経」ルートは、スピードは早いが、効果は一時的
・「内分泌」ルートは、血中に入り、スピードは遅いが、効果は長期間
(3)ホルモンの分泌量を調整する「視床下部」
・各内分泌器官からの情報でホルモンの分泌量を調整する。
・加齢により、視床下部の調整機能も、各内分泌器官の機能も低下する
・加齢で変化する代表的なホルモンは、メラトニン、成長ホルモン、テストステロン、エストロゲン、プロゲステロン、甲状腺ホルモン、コルチゾール、インスリン
2.最強ホルモン「DHEA」(ホルモンの母)
「DHEA」は副腎皮質でコレステロールから合成されるステロイド系ホルモンで、以下の特徴を有している。
(1)体内にもっとも多く存在するホルモン
(2)50種類以上の他のホルモンの原料になる
(3)多くのホルモンの代わりとなって作用する
(4)長寿のヒトの血中「DHEA」濃度が高い。但し、異常に高い場合は副腎皮質腺腫などの疑いがある。
(5)筋肉の維持・増強には「運動」と「たんぱく質」の摂取に「DHEA」を加えると効果はより大きくなる。
Ⅱ 「DHEA」の低下ストレスと増加方法
1.「DHEA」を低下させるストレス
(1)活性酸素によるストレス
運動すると、アドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾールの血中濃度は上昇する一方、「DHEA」は活性酸素を除去し、尿として排出される。
(2)糖化ストレス
糖質由来のアルデヒドとたんぱく質が結合し、AGE(終末糖化産物)が作られ、それが「DHEA」を低下させる。
2.日常的に「DHEA」を増やす最短の道
現在、「DHEA」は保険適用外の医薬品として認可され、不妊治療にもっとも多く使用されている。従って、ドラックストアなどで手軽に入手することはできません。
(1)運動
運動すると体に負荷がかかり直後には「DHEA」は減りますが、筋肉を鍛えることで「DHEA」の分泌量は増えます。なお、運動の種類には関係せず、ウォーキング程度でも増えます。
(2)質の良い睡眠
質の良い睡眠は成長ホルモン、メラトニン、そして「DHEA」の分泌を増加させます。
不定愁訴の緩和から、見た目や肉体の改善まで!
「老化」はホルモンで治せる!
2024年5月2日 9:05 カテゴリー:書籍紹介
《ゴールデンウィーク期間の営業日のお知らせ》
平素より格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。
誠に勝手ながら、弊社では下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
【休業期間】2024年 4月27日(土)~4月29日(月)
【休業期間】2024年 5月3日(金)~5月6日(月)
なお、2024年4月30日(火)~5月2日(木)は通常営業をしています。
営業日以外でもFAX・メール・Webサイトからのご注文は通常通り承りますが、商品発送は5月7日(火)以降となりますのでご了承ください。
ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
2024年4月25日 14:08 カテゴリー:お知らせ
書籍紹介「体質は3年で変わる」中尾光善 著
「体質は3年で変わる」
中尾光善 著 ISBN978-4-08-721269-3
最新の研究とテクノロジーによって、体質は遺伝だけでなく多様な環境との相互作用によって決まるものであり、体質に関わる遺伝子は環境の影響を受けやすいことが分かってきた。体質は変わる、変えられる。それにはどれくらいの時間がかかるのか。そこで著者が提唱するのが「体質3年説」だ。
1.体質は遺伝か環境か
(1)体質とは
医学的には体質は形質、気質、素質を総合したもので、それぞれは個体の保有している形態的、精神的、機能的性質を示す。
・形態的性質…体型や体格、顔立ちなど
・精神的性質…気性、性格など
・機能的性質…生まれ持った性質、資質、得手不得手など
(2)遺伝か環境か
・DNAの塩基配列は、1つの生物種では基本的に同じ。ヒトの場合、同じである割合は約99.9%で、違う割合はわずか0.1%程度。
・一卵性双生児はゲノムは同じですが、成長につれて外見的に微妙な違いが生まれ、性格も、かかる病気もまったく同じでないケースが多い。
2.体質を決める5つのしくみ(相互関連性)
(1)一塩基多型…血液型、毛髪や目の色を決める
(2)ポリジーン遺伝…身長、体重、血圧、知能などを決める
(3)エピゲノム…遺伝子にオン/オフの印をつける
(4)非コードRNA…遺伝子の働きに直接作用する
(5)複合的で未知なしくみの可能性…ミトコンドリア、エクソソーム、腸内フローラなど
3.3年で体質は変わる・変えられる
(1)多くの細胞は3年で入れかわる。
(2)乱れた食事習慣を3年で改善する。
(3)3年のトレーニングで病気になりにくい体をつくる。
4.ミトコンドリアの活性化(運動・寒さ・空腹が体全体の新陳代謝を促す)
(1)運動することで体内の余分なエネルギーを消費する。
(2)寒さを克服するために、体温を上げれば、蓄えたエネルギーを消費する。
(3)空腹になると蓄えたエネルギーを消費する。
生命科学が解き明かす人体の不思議
ゲノムの0.1%プラス環境因子が体質の違いを生む!!
2024年4月18日 9:01 カテゴリー:書籍紹介