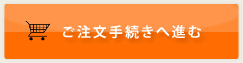書籍紹介「本当はこわい排尿障害」 高橋知宏 著
本当はこわい排尿障害
高橋知宏 著 ISBN978-4-08-721063-7
膀胱の構造は、次の3つに分けることができます。
(1)膨らんだり収縮したりするタンクである膀胱本体(膀胱体部)
(2)膀胱の出口にあたる膀胱頸部
(3)膀胱の出口付近から尿道へ伸びるセンサーでかつ原動機である膀胱三角部
膀胱本体は一定の量まで尿を溜め膨らみ、脳中枢の許可が下りると、膀胱を収縮させながら膀胱の出口を開き(膀胱頸部がゆるんで開く)尿を尿道に押し流して排尿します。排尿障害の患者さんは、様々な原因でこの膀胱頸部が十分に開かなくなり排尿障害になります。そして、膀胱頸部が十分に開かないために膀胱炎の症状が現れていることがわかります。
では、なぜ膀胱頸部が十分に開かなくなるのかといえば、その一つの原因は膀胱三角部が敏感になりすぎたり、あるいは変形してしまうからです。膀胱三角部を支配する神経は他の二者より、はるかに鋭敏で、他の二者が鋭く反応しないような小さな刺激であっても実に鋭く反応します。そのため膀胱本体に尿が溜まってくると、膀胱が膨らんで内圧が高っまたという情報を最初に感知するのは膀胱三角部になります。
また、膀胱三角部は共同して働き、膀胱の出口を排尿しやすい形状にします。しかし、膀胱三角部が過敏になると、膀胱に少しでも尿が溜まると排尿したいという情報を発信し、頻尿になったり、膀胱三角部が何らかの原因で正常に収縮しないと膀胱の出口は尿を排出しやすい形状になりません。つまり、十分開かなくなります。それでも尿を無理に出そうとするため、膀胱三角部と膀胱頸部は変形し、コントロールできなくなり、膀胱の出口がますます開かなくなります。
このようなプロセスにより排尿障害になると、膀胱や前立腺、尿道から脊髄中枢へ発信される情報が混乱したり、多くなりなりすぎ、脊髄中枢の様々な神経を刺激して、脳の情報処理を誤らせるので、身体のあちこちに痒み、痺れ、痛みなどの症状が出てくることになります。泌尿器科の専門医が解き明かす膀胱と排尿の秘密。
その陰部の痒み、排尿障害かもしれません?!
2019年6月6日 8:51 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「老いと記憶」増本康平 著
老いと記憶
増本康平 著 ISBN978-4-12-102521-0
加齢が脳に及ぼす影響で不思議なのは、年齢とともに脳全体に均質に変化がみられるわけではない事です。顕著に萎縮する場所とそれほど萎縮しない場所が存在します。
前頭前野の体積が加齢とともに最も萎縮し、次いで、海馬を含む側頭葉、頭頂葉、後頭葉の順に萎縮がみられます。加齢にともなう脳の変化には、このような神経細胞の減少にともなう萎縮と、もう一つ、シナプスの密度の低下があります。シナプスの密度の変化は特に前頭葉で顕著です。シナプスの密度の減少と認知機能低下は同時期に生じることから、神経細胞そのものの減少よりも、神経細胞間のネットワークの減少が認知機能の低下の原因であることが指摘されています。
なお、加齢とともに衰える記憶機能は二つです。一つは、短期記憶の「ワーキングメモリ」と呼ばれる複雑な思考や並列的な作業を担う記憶です。もう一つは長期記憶の「エピソード記憶」と呼ばれる過去に出来事の記憶です。但し、エピソード記憶の低下は全てのエピソードにみられるわけではなく、5年以内の比較的最近の出来事で顕著にみられます。
一方、私たちが経験したことを記憶し、それを思い出すためには、経験を情報として頭に入力し(符号化)、その情報を保持して(貯蔵)、保持した情報から必要な情報を思い出す(検索)という3つのプロセスを経る必要があります。年をとると特に低下するのは、情報の入力と検索のプロセスです。その理由は、加齢にともなう萎縮が顕著な前頭前野が、その両者のプロセスを担っているためです。
以上のような背景を前提として、本書は、高齢者心理学の立場から、若年者と高齢者の記憶の違いや、認知機能の変化など、老化の実態を解説。気分や運動、コミュニケーションなどが記憶に与える影響にも触れ、人間の生涯で記憶の持つ意味をも問うています。
加齢をネガティブに捉えず、老いを前向きに受け入れるヒントが見えてくる!!
2019年5月23日 8:47 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「自分が高齢になるということ」和田秀樹 著
自分が高齢になるということ
和田秀樹 著 ISBN978-4-86081-572-1
肉体的な衰えは、ウォーキングやジムに通ったり、あるいは日常生活の中に少しでも身体を動かすことを取り入ることにより、ある程度、意識的に遅らせることができます。
しかし、頭脳の衰えは意識すれば食い止めることができるかどうかはわかりません。ところが、高齢になるにしたがって、どんな人にも予測のできない状態が訪れる可能性があり、しかもその可能性は、高齢になればなるほど高まってきます。脳の変化とそれに伴う様々な変化です。
だれもが真っ先に思い浮かべるのが認知症でしょう。85歳という年齢を過ぎれば40%(55.5%という統計もある)程度の人に認知症の症状が現れます。だとすると、ボケることを前提にして、幸せなボケ、ボケてもいいから幸せな老人を目指したほうが、ゆったりとした気持ちで生きられるし、それによって長生きもできるはずです。
そこで、本書には、朗らかなボケ、穏やかなボケを目指すためにどうすればいいのかという視点で、高齢者専門の精神医学を学び、実践してきた著者が気づいたこと、考えていることがざっくばらんに書かれています。
ボケれば「嫌なこと」「つまらないこと」を忘れることができ、自責感からも解放され「わたしのせい」という周囲への心苦しさをあまり意識することはなくなります。また、ボケはゆっくりと進み、脳にはまだ活用できる機能が残されているので早期に適切な治療を受ければ、その進行をある程度遅らせることもできますから、たとえ認知症とわかってもいままでと通りにできることはいくらでもあります。そして、愛されるボケには周囲の人を幸せにする力があります。
老いて幸せなら人生それでよし!!
2019年5月9日 8:48 カテゴリー:書籍紹介