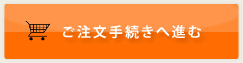書籍紹介「子育てのきほん」佐々木正美 著
「子育てのきほん」
佐々木正美 著 ISBN978-4-591-16121-0
子育てで何より大切なのは「子どもが喜ぶこと」をしてあげることです。そして、そのことを「自分自身の喜び」とすることです。子どもは、可愛がられるからいい子になります。可愛い子だから、可愛いがるのではないのです。いくら抱いても、いくら甘やかしてもいい。たくさんの喜びと笑顔を親と共にした子どもは、やがて人の悲しみを知ることができるようになります。誰とでも喜びと悲しみを分け合える人に成長するでしょう。これは人間が生きていくうえで、最も大切な、そして素晴らしい力です。
(1)悲しみを分かち合う力は意識的に「育てる」ものではなく、子どもが喜ぶことを喜んであげるなかで、喜びを親子で共有することしか育ちません。他者の心の痛みや悲しみを理解する「思いやり」は、共に喜び合うことを知って、初めて育っていくものなのです。
(2)親子、先生と生徒、医師と患者、はどんな関係でも「与え合う」ことが最高の人間関係です。従って、母親が幼い我が子と一緒にいることを幸せだと感じていれば、その幼子はお母さんと一緒にいることが何よりも幸せだということです。
(3)子どもの話を聞くことと、質問することは違います。問い詰めずに、子どもに話させてやって下さい。子どもは、そんなに簡単に「今、どんな問題があるのか」「何がイヤだと思うのか」なんてことを答えられるはずがありません。大事なのは、それがどんなに論理的でなくても、めちゃくちゃでも、耳をじっと傾けて、何をして欲しいかをくみ取ろうとしてあげなさい。
(4)親は「教育者」になってはいけない。これは絶対にいけない。親は保護者です。絶対的な保護者であって欲しい。
(5)子どもには、まず、母性的(容認)なものを先に十分に与え、その後から父性的(しつけ)なものを与えるべき。母性と父性は「バランス」ではなくて「順序」が肝心だということ。
親が望む子どもに育てるのではなく、子どもが望む親になって下さい!!没後も愛され続ける児童精神科医からのメッセージです。
2019年10月3日 8:43 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「知ってはいけない薬のカラクリ」 谷本哲也 著
知ってはいけない薬のカラクリ
谷本哲也 著 ISBN978-4-09-825344-9
実は製薬会社が一般の患者に向けて処方薬の宣伝を直接行うことは、政府により禁じられています。
処方薬は、正式には医療用医薬品と呼ばれます。医療用医薬品は、薬として効き目が強い反面、副作用にも注意が必要です。そのため、医者が診察した上で、数ある薬の中からどれがいいのか選ぶ必要があるということになっています。
つまり、処方薬選びは、医者の裁量が大きく、仕組み上、製薬会社の取引相手は患者ではなく、医者になっているわけです。そこで、処方薬を売る製薬会社は潤沢な資金力を使って、患者の目に触れないところで、医者向けにさかんに宣伝活動を行っています。それを象徴的に示しているのが、新薬の説明会で製薬会社が医者に無料で配る「高級弁当」です。しかし、薬の宣伝のために、考えられないくらいもっと大きなお金が動いています。多くの医師を集めてしばしば新薬の治療成績について説明が行われますが、大学教授がその新薬の“広告塔”となり、多額の謝礼金が支払われています。さらに、驚くべきことに製薬会社から薬価の算定委員にも多額の謝礼金が提供されていることも分かりました。
このような「白い巨塔の金脈」を明らかにしようと取り組んでいるのが、本書で紹介されているマネーデータベース「製薬会社と医師」プロジェクトです。探査ジャーナリズム活動を行う「ワセダクロニクル」と「医療ガバナンス研究所」に関係する著者たち医師グループにより製薬会社から医者個人へ流れるお金を調査報道によって明らかにし、分析を加え、日本初のデータベースをインターネット上で公開されています。
本書ではマネーデータベース「製薬会社と医師」プロジェクトから分かった知見を紹介するととともに、あなたの代わりに医者が薬を選ぶ背景について、つまり医者が処方薬を選ぶまでの裏側を分かりやすく解説しています。
現役医師が勇気をもって明かす“不都合な真実”
2019年9月19日 8:41 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「Dr.石原のお悩み相談室」 石原結實 著
Dr.石原のお悩み相談室
石原結實 著 ISBN978-4-7593-1664-3
漢方医学には2000年も前から「万病一元、血液の汚れから生ず」という概念があります。当時は血液の状態や内容などがまったくわかっていなかったので、この概念は多分に哲学的なものだったわけです。しかし、血液の構成成分や内容をすべて把握している西洋医学を通してこれを解釈すると、漢方医学の病因論は、まさに正鵠を射た表現であることがわかります。なお、血液を汚す原因として主に以下の(1)~(4)があります。
(1)「食べ過ぎ」
血液中の糖や脂質、タンパク質、老廃物の増加
(2)「食物の質」の間違い
肉、卵、牛乳、バター、マヨネーズに代表される動物性食品の摂取過剰による血液中の脂肪、タンパク質、老廃物の増加
(3)「運動不足」
体温生成要因の40%を占める筋肉を使った運動・労働が不足すると、血液中の糖、脂肪、タンパク質、老廃物の燃焼、利用が妨げられて、血液を汚す。
(4)「冷え」
冷える(体温低下)と、血液中の糖、脂肪、タンパク質などの栄養素や老廃物の燃焼、排泄が妨げられ血液を汚す。
一方、血液が汚れれば、体は何とか血液を浄化しようとします。この血液浄化反応としては、主に以下の(1)~(4)が挙げられます。
(1)発疹(湿疹、じんましん、化膿疹など)
(2)炎症(気管支炎、肺炎、胆のう炎、膀胱炎など)
(3)動脈硬化、高血圧、出血、血栓、結石
(4)がん腫(出血により血液の汚れを浄化)
ところが、西洋医学はこの血液浄化反応を「病気」と見て、抑えようとしている(対症療法)。しかし、食べ過ぎ、運動不足…など血液を汚す生活を続けていれば、血液は汚れたままで、根本的な解決になりません。
「血液の汚れ」と「血液の浄化反応」と考えれば、病気・症状に対する根本的な対処法、治療法が見えてくる!!
2019年9月5日 8:52 カテゴリー:書籍紹介