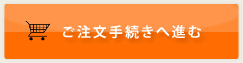書籍紹介「病気にならない新常識」古川哲史 著
病気にならない新常識
古川哲史 著 ISBN978-4-10-610890-7
病気予防は「食事」「運動」「睡眠」「ストレス」の4つが鍵を握っていますが、それらの常識は以下の様に次々と上書きされています。
1.食事
(1)満腹中枢を刺激するシグナル
満腹シグナルは ①胃が膨らむ事 ②血糖が上昇する事 ③噛む事 がありますが、③は唯一食べ過ぎる前に満腹中枢を刺激します。
(2)理想の食事は1975年の日本食
他の年代に比べて魚・果物・野菜・海藻・大豆製品・出し汁・発酵系調味料など植物性タンパク質、不飽和脂肪酸が多く含まれています。
2.運動
(1)有酸素運動は脳のサイズを大きくする。
海馬のサイズを大きくし記憶力の改善につながる。
(2)海馬の萎縮を予防する心房利尿ペプチド(ANP)
ANPは腎臓に作用して尿量を増やしたり、増えた心拍数を元に戻す事で心臓の負担を軽減します。
3.睡眠
(1)記憶と睡眠
ノンレム睡眠中に海馬で一時的に保管されている記憶を、大脳皮質に移動させて「長期記憶」にします。さらに、レム睡眠中にその記憶を呼び出しやすくする様に整理します。
4.ストレス
(1)ストレスによって起こる2つの反応
ストレスホルモンが出ると、交感神経が活性化され、交感神経が活性化されると「視床下部➡下垂体➡副腎」軸が活性化され、ストレスホルモンが分泌されます。
(2)苦味を強く感じる人は、ウィルスや細菌の防御力が強い
線毛活動、一酸化窒素の産生および、ディフェンシン(タンパク質)の生成作用により苦味受容体が防御します。
2021年10月7日 8:51 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「ライフサイエンス」吉森 保 著
ライフサイエンス
吉森 保 著 ISBN978-4-8222-8866-2
本書では、生命の基本単位である細胞について学び、次に病気について学びます。どんな病気でも必ず「細胞が悪くなっている」。つまり、病気だと感じた時はすでに細胞に何かが起きています。そして、細胞を「若返らせる」機能であり、著者の専門でもあるオートファジーについて学び細胞や病気の研究の最前線に触れる事ができます。「細胞がおかしくなる」中で一番大きいのは、細胞が死んでしまう場合ですが、その代表例は次の3つです。 (1)細胞内にタンパク質の塊が溜まって、その結果死んでしまう(ex.アルツハイマー病、パーキンソン病) (2)ウィルスなどの病原体に殺される(ex.インフルエンザ、新型コロナウィルス感染) (3)細胞内の「原発事故」(ミトコンドリアの崩壊)が原因で細胞が死ぬケース(ex.がん、心不全)。なお、細胞を「若返らせる」機能であるオートファジーの要点は以下の通りです。
(1)オートファジーのプロセス
オートファジーは「細胞の中の物を回収して、分解するリサイクル現象の事で ①平たい隔離膜が形成➡ ②膜を伸長させて、タンパク質やオルガネラ(細胞小器官)を包み込みオートファゴソームを形成➡ ③消化酵素が入ったリソソームと結合しオートリソソームの形成➡ ④タンパク質などが分解されオートリソソームの小さな穴を抜けてアミノ酸などが再利用される。
(2)オートファジーの役割
①飢餓状態になった時に、細胞の中身を分解して栄養源にする
②細胞の新陳代謝を行う・・・毎日240gのタンパク質を分解し再利用
③細胞内の有害物質を除去する・・・例えば、病原体を除去する自然免疫能
(3)オートファジーを止める「ルビコン」
オートファジーのブレーキ役となるルビコンは高脂肪食により肝臓で増え、老化によっても増える。
(4)オートファジーが防御的に働くと考えられる代表的な病気
①生活習慣病 ②神経変性疾患 ③肝臓がん ④腎臓の病気 ⑤心不全
(5)オートファジーを活性化させる天然の成分
代表的なものに「スペルミジン」があり、納豆などの豆類や発酵食品、シイタケなどのキノコ類に多く含まれています。なお、「スペルミジン」は体内でアミノ酸から作られますが、老化により作る量は激減します。
長生きせざるをえない時代の生命科学講義!!
2021年9月16日 8:59 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「新型コロナワクチン本当の『真実』」宮坂昌之 著
新型コロナワクチン本当の「真実」
宮坂昌之 著 ISBN978-4-06-525679ー4
本書は、免疫学の第一人者である著者が、新型コロナウィルスとワクチンに関する最新の科学的知見を分析して、一般の方々にぜひ知っていただきたい情報をまとめたものです。ワクチン接種の是非が最大の関心事と思われますので、本コーナーでは「嫌ワクチン本」などの誤解についてのみご紹介する事に致します。
1.感染を防ぐには上気道の粘膜上皮に「IgA抗体」の存在が不可欠ですが、「注射タイプ」のワクチンでは、作られるのは「IgG抗体」であり、血中を循環しても粘膜上皮に現れない。
⬇
今のmRNAワクチンは接種後に血中にIgG、IgAの両方の抗体が現れ、その一部は粘膜面へ移行するのでウィルス防御の役割を果たす。
2.遺伝子ワクチンではウィルス遺伝子の一部がどの細胞に入るかわからず、特定の細胞にウィルス遺伝子が導入され発現すると、その細胞は異物と見なされ免疫細胞に攻撃され、自己免疫疾患が起こりかねない。
⬇
mRNAワクチンは、注射局所の細胞にmRNAが入らず、ワクチンそのものがリンパ管を介して主に所属リンパ節に運ばれ、そこに存在する樹状細胞に取り込まれ、細胞内でスパイクタンパク質が作られる。その後、スパイクタンパク質が分解され、それが樹状細胞表面で抗原として提示され、一連の免疫反応が開始される。さらに、樹状細胞もその内で発現するmRNAの寿命も数日以内なので、スパイクタンパク質がT細胞やB細胞を刺激し続ける事はありません。
3.mRNAの運び役の脂質がアジュバント(免疫増強物質)として働く事でワクチン接種後に強い副作用が発現する。
⬇
運び役の脂質は①mRNAの安定性の向上 ②リンパ管に入りやすい ③樹状細胞に取り込まれやすい など予想を超える働きで、非常に好ましい形の免疫反応を起こす。
コロナワクチン解説書の「決定版」がついに登場!!
2021年9月2日 9:01 カテゴリー:書籍紹介