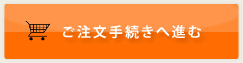書籍紹介「やはり死ぬのは、がんがよかった」中村仁一 著
やはり死ぬのは、がんがよかった
中村仁一 著 ISBN978-4-344-98617-6
人間は本来、穏やかな死を迎えられる様になっています。それを邪魔しているのが「延命医療」と“延命介護”ではないかと思います。著者もそうでしたが、同和園(社会福祉法人老人ホーム)でがん死された皆さんは、全員、手遅れで見つかっています。どうしてかというと、痛みが無いからです。痛みに苦しむ事が無ければ、最期の日が訪れるまでに身辺整理ができ、お世話になった人たちにお礼やお別れをいう事ができます。まさに“がんの自然死”は願ってもない死に方といえるのです。
自然死とは、一言でいうと「餓死」する事ですが「死に際」のそれは、命の火が消えかかっているわけですから、食欲も無ければ、喉も乾きません。脱水状態になると、意識レベルが下がり、“脳内麻薬”のβ-エンドルフィンが分泌され、ウトウトとしたいい気持ちになります。死に近くなっても、体内の臓器は動いていますので、肝臓と筋肉に蓄えられているグリコーゲンも消費され、代わりに脂肪がエネルギー源となります。脂肪は分解される、水と炭酸ガスとケトン体になり、ケトン体には鎮静作用があります。なお、「脱水」の状況下では冷却不足のため、体温が39度くらいまで上昇する事もあります。
発達したと言われる近代医療に過度の期待を持ち、老いを「病」にすり替えています。年寄りの不具合は、すべて老化が原因か、老化がらみです。今さら、医者にかかって薬を飲んでも根本的には、どうなるものではありません。生活習慣病の特徴は、「治らない」「治せない」「予防できない」「すぐには死なない」です。なぜ、治らなのか。それは一言で言えば、うつらない病気だからです。さらに専門医がいるため、話がややこしくなります。だいたい「早期発見」「早期治療」は、完治の手立てのある、肺結核での手法であり、これを完治のない生活習慣病に適用しても、そもそも無理があります。また、いくら病気について詳細にわかっても、それを好転させる手立てが存在しなければ、大した意味もありません。
無治療のがん患者を大勢看取り、自身も末期がんになった医師だからわかる事!!
2021年11月18日 8:09 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「光免疫療法」小林久隆 著
光免疫療法
小林久隆 著 ISBN978-4-334-04519-7
光免疫療法は、がん細胞を制圧する治療法で、まずは、がん細胞だけに特異的に結合する抗体を使用し、この抗体に近赤外線によって化学反応を起こす物質IR700を搭載し、静脈注射で体内に注入する。がん細胞膜表面のタンパク質に結合した抗体を目印に近赤外光を照射すると、組み込まれたIR700が反応し、それまで水溶性だった性質が一変し、水に対して不溶性の物質に変化する。そこで、結合した抗原と抗体は不溶性となったIR700を覆おうとするため、抗原が引っ張られて細胞膜に1万個程度の傷がつく。この傷により細胞膜が外からの水の流入に耐えられなくなり、流入した水でがん細胞は急激に膨張・破裂して、抗体のついたがん細胞のみがバタバタと破壊される。この一連のプロセスが光免疫療法の基本的な仕組みです。ここでの抗体は、直接にがんを死滅させる役目を持つわけでもなく、いわば爆弾の「運び屋的」な役割を担うものです。
なお、この様な基本的な仕組み以外に以下の様な機能や特徴があります。
(1)転移がんや再発も抑制する
成熟した樹状細胞が、破壊されたがん細胞から放出される抗原を食べて、抗原情報をリンパ球に伝える。リンパ球は生き残ったがん細胞や、余力があれば転移しているがん細胞を攻撃しに行く。それゆえ、最初からがんを100%殺さなくても構わないし、さらに薬剤などの集積毒性もないので、何度でもこの治療を行う事ができる。
(2)がんの共犯者を叩く
がん細胞をかくまっているTreg細胞などの免疫抑制細胞も特異抗体にIR700を乗せて近赤外光の照射で破壊する。
(3)メモリーT細胞を作る
(4)患部がきれいに修復され、瘢痕を残さない。
(5)他の治療に比較してコストが安い。
NIH(アメリカ国立衛生研究所)の日本人開発者による身体にやさしい新治療ががん医療変える!
2021年11月4日 8:47 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「『エビデンス』の落とし穴 」 松村むつみ 著
「エビデンス」の落とし穴
松村むつみ 著 ISBN978-4-413-04613-8
健康情報については「結局のところ、その健康法は体にいいのか悪いのか」という「答え」を知りたと思う方が多いと思います。そのためにも、そもそもエビデンス(科学的根拠)が何であるのか、どういう仕組みでエビデンスの評価がなされ「信頼できるエビデンス」が築かれていくのかを知っておく必要があります。ひとくちに「エビデンスあり」と言っても、実はエビデンスには様々な段階=ランクがある事は、一般にあまり知られていません。医学の世界では、エビデンスの信頼性の強弱を「エビデンスレベル」と言い以下の様にレベル1から6に分けられ、レベル1が最も信頼性が高く、レベル6が最も信頼性が低くなります。
【エビデンス6】「専門家の意見」
具体的なデータなどに基づかない「専門家の意見」で、医学専門誌に掲載される様な専門家の意見もここに入ります。
【エビデンス5】「症例報告」
専門の教科書に載っていない珍しい症例や、通常の治療は効かなかったけれど、特定の治療を試したら効果があった様な症例の論文や学会発表
【エビデンス4】「症例対照研究」「コホート研究」
過去に遡るって、病気の原因などについて研究したり、大規模な疫学調査による研究
【エビデンス3】「非ランダム化比較試験」
【エビデンス2】「ランダム化比較試験」
例えば、新しい薬の効果を確かめる際に、参加する患者さんを二つのグループに分け、一方のグループには新しい薬を投与し、もう一方のグループには、ニセの薬(人体に無害)を投与する場合のグループ割りをランダムに行うか否かによる違い。
【エビデンス1】「システムマティックレビュー」「メタアナリシス」
複数の研究を統合して、結果を出したもので、通常このプロセスを経て、専門分野ごとに「診断や治療のガイドライン」が作成される。
どれも「エビデンスあり」なのに正反対の情報が出てくるのはなぜ!?
2021年10月21日 9:00 カテゴリー:書籍紹介