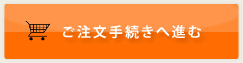書籍紹介「肝臓のはなし」竹原徹郎 著
「肝臓のはなし」
竹原徹郎 著 ISBN-978-4-12-102689-7
今回は前回に続いて、「肝臓の主な病気」を取り扱います。
Ⅱ 肝臓の主な病気
1.黄疸(赤血球のビリルビンの処理)
(1)120日ほどの寿命の赤血球は主に脾臓で破壊され、黄色の色素ビリルビンに変換されます。
(2)不溶性のビリルビンはアルブミンと結合し肝臓に運ばれ、肝臓は水溶液のビリルビン(抱合)にして胆管に流します。
(3)その後、水溶液のビリルビンは「胆汁」の一部として胆道を経て十二指腸から消化管に排泄されます。
(4)黄疸は赤血球の破壊が過剰になると生じたり(新生児黄疸)、肝臓の病気や胆汁が胆道から消化管に排泄されない場合にも生じます。
2.肝炎ウイルス
(1)肝炎ウイルスはA型、B型、C型、D型及びE型の5種類に分類されます(発見の順位はB型→A型→D型→E型→C型)。
(2)A型とE型は「流行性肝炎」の原因になるウイルスで急性肝炎を起こしますが、持続感染はありません。
(3)両型ともにウイルスに汚染された水や飲食を介して感染し、A型は魚介類、E型は食肉を介して感染することがあります。
(4)D型は特異なウイルスでB型に感染している状況においてのみ感染性ウイルスを作る「欠損ウイルス」です。
(5)B型とC型は「血清肝炎」の原因になるウイルスで、体液や血液を介して感染し、持続感染します。
(6)B型肝炎に対する薬剤はウイルスの複製を阻害する核酸アナログ製剤が用いられます。複製を抑制するだけなので、ずっと飲み続ける必要があります。
(7)C型肝炎に対する薬剤はウイルスの特定の分子の機能を抑制するDAAが使用されます。高額な薬剤ですが、2週間位の服用で完了します。
3.肝臓がん
(1)年間約5万人の方が肝臓の病気で亡くなりますが、劇症肝炎(急性肝不全)は数千人で、残りの大多数は慢性肝疾患です。
(2)慢性肝疾患の原因は肝炎ウイルス、脂肪肝、アルコール、自己免疫など様々ですが、プロセスは、肝臓の慢性炎症→硬化(線維化)→がん化という同一の流れになります。
(3)肝臓がんには「肝細胞がん」と「胆管細胞がん」の2種類がありますが、約9割は肝細胞がんです。
(4)肝臓がん診療の特徴は以下の3つです。
・腫瘍生検よりも画像診断が重視される(超音波検査→造影剤を用いたCTやMRI)。
・治療法の選択には肝臓の残存予備能力が問題になります。
・慢性肝疾患から発生するので再発が多い(異所性発がん・異時性発がん)。
(5)治療法は早期であれば、ラジオ波焼灼治療あるいは外科的切除、中程度であれば肝動脈化学塞栓療法、重度であれば様々な抗がん剤治療が行われます。
4.肝硬変
(1)肝臓が線維に置き換わることにより肝硬変が生じ、肝臓の機能が損なわれる「肝不全」に到ります。
(2)また、線維化し、肝臓が硬くなると、門脈からの血流が堰き止められ「門脈圧亢進症」が発生します。
(3)肝臓はあまりにも機能が複雑なために、人工臓器は実用化されていません。従って、肝不全になると他者からの肝移植することが究極治療になります。
(4)肝移植では、免疫抑制治療などが必要になりますが、移植後6ヶ月以内に約20%で発生する合併症を乗り越えると、その後は長期にわたって元気に暮らせます。
(5)門脈圧亢進症になると、側副血行路(シャント)ができて、肝臓を介さずに血流が心臓に還っていきます。
(6)すると、食道静脈瘤や胃静脈瘤ができ、それらが破裂すると大出血を起こし吐血や下血をし、命にかかわることになります。
(7)側副血行路が形成されると門脈に流入する血液が全身に入り、感染症が起こりやすくなったり、肝臓が萎縮したりします。
(8)また、アンモニアを含んだ血液が直接心臓に入り、頭にめぐると「肝性脳症」が起こりやすくなります。
(9)さらに、腸管から吸収されたグルコースも肝臓を素通りし、血糖のコントロールも不良になります。
2024年12月19日 9:02 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「肝臓のはなし」竹原徹郎 著
「肝臓のはなし」
竹原徹郎 著 ISBN-978-4-12-102689-7
現代の日本人は、4~5人に一人の割合で、肝機能に異常があるとされています。肝臓は「予備能」と「再生能」を有する「代謝の中枢臓器」です。今回は「肝臓の仕事」を、次回は「肝臓の主な病気」を取り扱います。
Ⅰ 肝臓の仕事
1.肝臓の血管の特徴
(1)臓器は流入血管として動脈(心臓に始まり毛細血管で終わる)、流出血管として静脈(毛細血管に始まり心臓で終わる)をもっていますが、肝臓だけはそれ以外に門脈をもっています。
(2)正常な肝臓は、肝動脈からの血流が3割に対して、門脈からの血流が7割となっています。
(3)門脈は具体的には、消化管や脾臓の毛細血管から始まり、肝臓の毛細血管で終わりますので、圧力が低く酸素の量も少なめです。その代わり、大量の栄養素を含んでいます。
2.グリコーゲンの合成と分解
(1)門脈からグルコースを取り込み、肝細胞自身のエネルギー源として利用する一方で、余分なグルコースはインスリンの作用によりグリコーゲンとして肝細胞と筋肉だけに蓄えます。
(2)血液中のグルコースが少なくなると、筋肉中のグリコーゲンは分解されて、筋肉のみ使用されます。一方で、肝臓のグリコーゲンはグルコースに分解され血液中に放出し、特に脳(90g/日)と赤血球(45g/日)で使用されます。
(3)肝臓は重さにして50~70gをグリコーゲンとして蓄えることができますので、一日三食の食生活は、グリコーゲンの蓄積・分解のサイクルに基づいています。
(4)飢餓状態になっても、脳が活動できるのは、肝臓がアミノ酸や乳酸など糖質以外からグルコースをつくり出す「糖新生」によります。
3.脂質の利用
(1)食間期にグルコースが枯渇すると、皮下や内臓周囲に溜まっている中性脂肪が分解され、脂肪酸を肝臓が取り込みエネルギーにします。
(2)取り込まれたエネルギーの多くは、肝細胞自身のエネルギーにならず、最後まで分解されないで、水に溶けるケトン体という中間産物になり、血液中に放出され、他の臓器の栄養源になります。
(3)過剰なグルコースの摂取は、容易に脂肪に転換されますが、反対に、脂肪をグルコースに転換することはできません(グリセロールを除く)。
(4)放出するよりもつくるほうが優勢になると、肝臓の中に中性脂肪が脂肪滴として蓄積されます(脂肪肝)。
(5)肝臓がつくるコレステロールは単なる悪者ではなく、細胞膜、ステロイドホルモン、ビタミンD、胆汁酸などの原料になります(医学的にはコレステロールが少ないほうが問題)。
4.タンパク質の合成
(1)血液中のタンパク質の半分以上は肝臓がつくる「アルブミン」で、血管の中に水を保持する作用をもっています。
(2)アルブミンが低下すると、血管外に水分が漏れて、浮腫や腹水の原因になります。
(3)さらに、肝臓は「凝固因子」という血液を固めるタンパク質群をつくっています。
(4)出血すると、まず「血小板」が凝集して傷口に蓋をします(一次血栓形成)。次に、血液中の「凝固因子」が活性化し血液を固めます(二次血栓形成)。
(5)前記以外にも、タンパク質の「補体」や炎症が起きると上昇するC反応性タンパク質(CRP)などもつくります。
5.尿素の合成
(1)三大栄養素は、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)でつくられていますが、タンパク質(アミノ酸)だけは、これ以外に窒素(N)を含んでいます。
(2)炭素は二酸化炭素として、水素は酸素と水として、それぞれ肺と腎臓から排出されます。
(3)一方、窒素からは、有害なアンモニア(NH3)が絶えず生成されます。そこで、肝臓は「尿素サイクル」によってアンモニアを無害な尿素に変換し、血流に乗って腎臓から排泄されます。
2024年12月5日 9:10 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「70歳までに脳とからだを健康にする科学」石浦章一 著
「70歳までに脳とからだを健康にする科学」
石浦章一 著 ISBN-978-4-480-07607-6
本書は、健康で長寿になれる方法を、生命科学の最近の知見に基づいて解説しています。
1.認知症(特にアルツハイマー病)
(1)認知症には、主にアルツハイマー型(63%)、血管性(15%)、レビー小体型(12%)、前頭側頭型(数%)があります。
(2)アルツハイマー病の特徴は①老人斑(アミロイドβタンパク質)、②神経原線維変化、③脳の萎縮の3つです。
(3)遺伝子変異(候補は3つ)で起きる若年性アルツハイマー病は全アルツハイマー病の1%です。
(4)このタイプは、優性遺伝病なので、変異遺伝子を1つ持っていると必ず発症します。従って、子供は50%の確率で発症します。
(5)老人斑(アミロイドβタンパク質)はアミロイド前駆体(APP)にあるAβ部分の先端で切断されると脳内に沈着します。
(6)普通の人がアルツハイマー病にならないのは、Aβ部分の真ん中で切断されるため、Aβタンパク質が沈着しないからです。
(7)実はダウン症の脳にも10代から老人斑が蓄積することが分かってきました。
(8)全ての人が持っているアポE(アポリポタンパク質E)遺伝子には、E2型、E3型及びE4型がありますが、E4型を2個持っている人は、日本人に一番多いE3型を2個持っている人の11.6倍もアルツハイマー病になりやすい。
(9)さらに、アポE4を持つ人は頭を打つ(ボクシング、アメフト、ラグビー、サッカー、プロレス)と特にアルツハイマー病になりやすい。
(10)加えて、アポE4を持つ人は、脳卒中からの回復が遅いことも分かってきました。
(11)そこで、アポE4は実はアルツハイマー病の素因遺伝子ではなく、脳の脆弱性の指標となる遺伝子ではないかと考えられるようになっています。
(12)一方、アポE2型を持っている人は100歳以上の長寿者に多い。
2.肥満とダイエット
(1)摂取した食料の利用効率は個人差があり、利用効率がよい人は太り、逆に、利用効率が悪い人はなかなか太りません。
(2)最大酸素摂取量で測定される基礎代謝(消費エネルギーの60%)は筋肉量にほぼ比例します。従って、筋肉量も運動量も減っている高齢者は太りやすくなります。
(3)タンパク質も糖質も過剰摂取すると脂肪として蓄積され、一方、使う場合は、体内に蓄積された糖質(筋肉・肝臓)が最初に使われ、次にタンパク質、そして最後に脂肪が使われます。
(4)減量すると臓器の重量も落ちます。一番落ちるのは腎臓、その次が肝臓、心臓、筋肉の順になります。従って、ダイエットは上手に行わないと危険な行為になります。
(5)摂取エネルギーの50~55%は炭水化物で摂取するのがベスト。それ以下でも以上でも死亡リスクが上がります。
3.筋肉と体力
(1)体力にはからだを動かす体力(運動能力)と測定が難しいからだを守る体力(免疫力)があります。
(2)骨格筋などの筋細胞が壊れると多核細胞の筋繊維の横にある金衛星細胞が分裂して、筋細胞が作られます。
(3)加齢により、白筋(速筋)の比率が増え、持久力がなくなりますので、持続的な運動で、赤筋(遅筋)を増やす必要があります。散歩やジョギングと同時に階段を上ることです。
(4)母乳のように必須アミノ酸9種類が全て揃っているのは肉、魚、卵、牛乳、大豆などです。
(5)タンパク質ばかり摂取して、炭水化物が少ないと筋肉は付きません。エネルギーの半分は主食で摂りましょう。
(6)豚肉や牛肉の脂肪は高温でないと溶けませんが、鶏肉の脂肪は低温で溶けおいしいので、お弁当に鶏肉のから揚げが多く使われます。
(7)ふとももが太いほど死亡率が下がり、細いと死亡率が上がります。太ももが太いということは運動をしている結果です。
本書では、以上のほかに、脳やバイオマーカーなどの最近の生命科学の話題と最新治療の話題についても解説してます。
科学でナットクの新常識!!
2024年11月21日 9:03 カテゴリー:書籍紹介