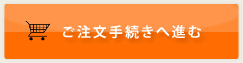書籍紹介「日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた」奥田昌子 著
「日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた」
奥田昌子 著 ISBN978-4-06-527456-9
Ⅰ 病気の「なりやすさ」と病気
病気に「なりやすい」からといっても、必ずしも病気に「なる」とは限りません。
1.病気の「なりやすさ」
親から受け継いだ遺伝子のタイプと遺伝子の働く強さが、病気の「なりやすさ」を決めています。そして、病気の「なりやすさ」(体の設計図)は基本的に生涯変わりません。
2.病気
親から受け継いだ病気の「なりやすさ」に以下の2つの変異が加わることで病気になります。
(1)生後に起きる遺伝子変異
生活習慣や環境により遺伝子に傷がつき望ましくない遺伝子変異により病気になる。
この変異は一度起こると戻すことはできません。
(2)生後に起きるエピジェネティクス変異
体の設計図は変化せずに、悪い生活習慣や環境によって、遺伝子発現のスイッチがオンやオフに切り替わる変異によって病気になる。但し、この変異は生活習慣や環境の改善によりリセットできることがあります。
(3)まとめ
前記の2つの差異による遺伝子への影響度は、体の設計図が生まれながらに決定しています。つまり、「遺伝」と「生活習慣と環境」は密接不可分の関係にあります。さらに遺伝子のスイッチのオンやオフがそのまま子孫に伝わる可能性があることも明らかになっています。
Ⅱ 日本人の「遺伝子」と「体質」の特徴
主な特徴は以下の通りです。
1.酒に弱い日本人はアセトアルデヒドを分解する酵素が少ない。稲作は感染症の危険が伴うことから、アセトアルデヒドが侵入した病原体の活動を抑制し、生存に有利に働いた可能性が考えられます。
2.日本人の胃は釣り針のように曲がった形の鉤状胃なので、食物繊維の多い穀物を食べるようにできている。
3.魚を多く食べてきた日本人は悪玉コレステロールにEPAやDHAが多く含まれて、動脈硬化になりにくい。
4.白筋の弱い日本人は筋力が弱く、内蔵を支えることができません。そこで、これを補うため内臓脂肪がつきやすくなり、一見痩せていても、生活習慣病になりやすい。
5.大腸がんや生活習慣病を予防するため、腸内の善玉菌の餌となる食物繊維をもっと摂取する必要がある。
生まれ持った「遺伝的な体質」は変えられる!
最近科学が示す「日本人が健康になる秘訣」とは
2023年12月7日 9:09 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「カオスなSDGs」酒井敏 著
「カオスなSDGs」
酒井敏 著 ISBN978-4-08-721259-4
近年声高に叫ばれる「SDGs」や「サステナブル」という言葉。環境問題などの重要性を感じながらも、レジ袋有料化や紙ストローの導入、SDGsバッジなどの取り組みに、モヤモヤしている人は少なくないでしょう。
国連の定義によれば、「持続可能な開発」とは「将来の世代がそのニーズを満たせる能力を損なうことなしに、現在のニーズを満たす開発」のこと。
SDGsは未来のために「いま」を犠牲にしろと言っているわけではなく、現在に生きる私たち自身のニーズを満たしながら、将来世代のニーズも満たしましょうという話です。とりわけ日本の場合、SDGsといえば脱炭素や脱プラスチックといった環境問題ばかり注目されますが、17の目標を見ればわかるとおり、そこには「環境」のほかに「経済」「社会」という大きな柱があります。これら3つの分野での持続可能性をどれも高めようとすれば、必ずどこかで優先順位をめぐるケンカが起きます。どこかで「キレイゴト」を引っ込めて、「大人の事情」に基づく調整が必要になります。
例えば、プラスチックの場合、完全なリサイクルにこだわらず、少しずつ品質を下げて、同じ素材を何度か使い、最後はエネルギー源として石油の代わりに燃やして熱回収するのが、一番サステナブルでしょう。
複雑系の研究の「カオス」では、因果律は存在していても、現在の状態から未来を予測することはできないし、過去にあったはずの原因を特定することはできません。
実際、IPCCも温暖化の予測を外しました。1990年代に報告されたIPCCのシミュレーションによれば、温暖化は加速度的に進むはずでしたが、1998年から約15年間、気温の上昇が停滞し、この「ハイエイタス」現象をIPCCは予測できませんでした。
「カオス」は「混沌」という意味ですから、秩序とは無縁のものに思えますが、じつはそうではない。未来は予測不能だけれども、そこにはある種の秩序が生まれてしまうのです。
ですから、SDGsの17の「ゴール」も、目指すべき正解では決してありません。
いまの私たちが少しでも楽しく幸福に暮らせるよう、破滅的な事態の発生を先送りにして、結果オーライで解決できるよう、時間稼ぎをすることはできるでしょう。
その意味で、SDGsは目指すべきゴールではなく、私たちが生き方を見直すためのスタートラインなのだと思います。
元京大変人講座教授SDGsにモヤモヤする!!
2023年11月16日 9:06 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「「心の病」の脳科学」林(高木)朗子 著・加藤忠史 編
書籍紹介「「心の病」の脳科学」
林(高木)朗子 著・加藤忠史 編 ISBN978-4-06-528363-9
心に起因する社会問題はますます深刻化しています。最新の疫学データによれば、精神疾患、つまり「心の病」に一生涯のうち一度でも罹患する確立は80%だそうです。そのような中、質の高い心豊かな生活をおくるためにはどうすれば良いでしょうか。そこには、人が人の脳を正しく理解する「脳リテラシー」こそが、「心の病」の予防や治療への鍵となります。「心の病」を治すのが難しいのは、私たちの脳はとても複雑な仕組みではたらいているからです。しかし、編者ら研究者は、決して精神疾患が不治の病であるとは考えていません。
本書は「心の病」がどうして生じるのか、そして、どこまで研究が進んでいるのかを最前線の科学の視点で解説し、大きく分けて以下の3部から構成されています。
第1部 「心の病」はどこから生じるのか?
「心の病」は脳のどこか不具合を起こし発症する疾患なのか。脳のはたらきを司るゲノム、神経細胞同士のつなぎ目であるシナプス、神経細胞がつながってできる脳回路の3つのスケールから考察します。
第2部 脳の変化が「心」にどう影響するか?
うつや不安、落ち着きのなさ、コミュニケーション障害、感覚過敏などこうした不調も、脳のちょっとした変化から生じる。最新研究から、精神疾患に関係する脳の変化を明らかにします。
第3部 「心の病」の治療への道筋
対処療法でしのぐしかなかった精神疾患の治療に転換期が訪れています。薬物治療だけでなく、ロボットやニューロフィードバックという新技術も進み、「治る病気」となる日も少しづつ近づいている状況を考察します。
なお、脳の疾患には精神疾患(心の病)と神経変性疾患があります。精神疾患では、神経細胞の顕著な細胞死は見られません。一方、神経変性疾患では脳や脊髄にある神経細胞が細胞死を起こします。しかし、両者には、神経細胞間の情報伝達に関わるシナプスの異常や細胞内の情報伝達やエネルギー産生に関わるミトコンドリア異常といった分子レベルの変化から症状が始まるという共通性があります。
うつ病、ADHD、自閉スペクトラム症、PTSD、統合失調症、双極性障害などは脳の中で何が起きているのか?
2023年11月2日 9:08 カテゴリー:書籍紹介