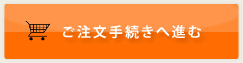書籍紹介「健診結果の読み方」永田宏 著
「健診結果の読み方」
永田宏 著 ISBN-978-4-06-535193-2
本書は健診で良く出てくる項目について、臓器別・病気別にまとめて解説しています。ここでは、その中でも特に近年、注目度の高い肝機能検査と腎機能検査について考察します。
1.肝機能検査
(1)代表的な検査は、血液検査によるAST、ALT及びγ-GTPの3つの酵素です。
(2)ASTは、肝臓以外に心筋や赤血球にも多く含まれるので、肝臓以外の病気でも上昇します。
(3)ALTは、肝臓や胆管にだけ多く存在しますので、血中濃度が上昇すれば、それらの臓器に問題があります。
(4)ALTがASTより高ければ、アルコール性肝炎、ASTのみ高いと心臓に問題がある可能性があります。
(5)γ-GTPは肝臓の解毒作用に関わる酵素なので、大量の飲酒で肝細胞が傷つくと血中濃度が上昇します。
(6)血中のビリルビンが高いと、先天的な体質でない限り、肝臓や胆道が悪いと考えられます。
(7)黄色い色素物質のビリルビンは、約4ヶ月で寿命がつき脾臓で破壊される赤血球のヘモグロビン(酵素運搬タンパク質)の老廃物です。
(8)分解されたビリルビンは血中に放出され、その後、肝臓で処理されて胆汁の一成分として十二指腸に放出され、最後は大便や尿として排泄されます。
(9)肝臓に問題があるとビリルビンのみならず、AST、ALTやγ-GTPの数値も高くなります。
(10)胆道に問題(胆石、胆管がん、膵臓がん)があって、胆道が詰まると、胆汁が排泄されなくなり、血中ビリルビン濃度が上昇し黄疸が出ます。
(11)慢性腎臓病(GLD)にはMAFLD、MAFLD、NASHがあります。
(12)MAFLD(代謝異常関連脂肪肝)は肥満、脂質異常症、2型糖尿などの代謝異常を伴った脂肪肝です(以前はアルコール性脂肪肝と呼ばれていました)。
(13)NAFLD(非アルコール性脂肪肝)は、お酒を(ほとんど)飲まないひとの脂肪肝で、進行するとNASH(非アルコール性脂肪肝炎)になります。
(14)今、日本では、飲酒やウイルスに関係しないNAFLDとNASHが増えています。放っておくと、少しずつ悪化し、肝硬変や肝臓がんになるリスクが増大します。
2.腎機能検査
(1)代表的な検査は、検尿による尿糖(GLU)、尿潜血(BLD)、尿蛋白(PRO)と血液検査によるクレアチニン(CRE)の4項目です。
(2)尿糖は、腎臓で回収し切れなかった血糖ですが、健康な人では尿に糖はほとんど出ません。
(3)空腹時血糖値やHbA1cにも異常が出ていれば、糖尿病が進んでいる可能性があります。
(4)尿潜血は、尿に肉眼では確認できない微量の血液が混じっている状態です。
(5)尿道炎、膀胱炎、痔や生理、尿路結石や腎臓がんや膀胱がんなどでも陽性になります。
(6)尿蛋白は血中に溶けているタンパク質が腎臓で十分に回収されず尿に出てきたもので、病気としては、慢性腎臓病、子宮体腎炎、糖尿病性腎症、高血圧性腎症などの可能性があります。
(7)激しい運動や感染症などで高熱が出た後や生理前後でも陽性になることがあります。
(8)クレアチニンは、慢性腎臓病(CKD)のスクリーニングになる項目で、CKDは糖尿病性腎症、高血圧性腎症、慢性糸球体腎炎、多発性のう胞腎などの病気の総称です。
(9)筋肉のエネルギー源の一種で、アミノ酸から合成されたクレアチンは骨格筋に蓄えられています。
(10)それが、運動で消費されると、老廃物のクレアチニンになって血中に溶け、腎臓から尿と一緒に排泄されます。従って、運動量が多いとクレアチニンは増加します。
(11)クレアチニンの供給量は筋肉量で決まり、排泄量は腎機能で決まります。
(12)筋肉量は加齢により減少しますので、供給量は減ります。しかし、腎機能が弱って、それ以上、排泄量が減ると血中にのクレアチニン濃度は上がります。
気になる項目について、パラッと読むだけで健診結果の見方が変わる!!
2025年2月6日 9:08 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「健康の分かれ道」久坂部羊 著
「健康の分かれ道」
久坂部羊 著 ISBN-978-4-04-082507-6
老いれば健康の維持がむずかしくなりのは当たり前。老いて健康を追い求めるのは、どんどん足の速くなる動物を追いかけるようなもの。予防医学にはキリがなく、医療には限界がある。
1.健康の入口
健康には「入口」があります。持病のある人は別として、子どものころから、青年期までは、常に健康を意識している人は少ないでしょう。しかし、ある年齢になると、健康が気になりはじめます。血圧や体重、血液検査の結果などが頭を離れなくなると、人は健康の「入口」に吸い込まれます。
2.健康の迷路
(1)症状もなく治療の必要もない「異常」を見つけて、精密検査を勧めたり、医療機関の受診を勧めたりする無駄と迷惑。
(2)検査の基準値を厳しくして、どんどん病人と判定。されたほうも納得し、感謝さえする現状。
(3)高血圧は動脈硬化の危険性を高め、心筋梗塞や脳梗塞などの病気につながります。しかし、動脈硬化は血圧以外に喫煙、肥満、高コレステロール症、糖尿病、運動不足なども危険因子になります。この事実を無視してそれぞれの学会は自分たちの基準だけを押しつける。
(4)超音波診断では、肝のう胞、肝血管腫、腎のう胞、腎石灰化など症状もなく、治療の必要もない異常を見つける。
(5)検診で早期がんが見つかり、手術を受けた人が命拾いしたと実感し、他人にも受診をすすめたりします。しかし、検診で見つかるがんは、手術しなくても命に関わらない可能性があります。
(6)2023年に承認されたアルツハイマー病に対する新薬レカネマブは、進行を遅くしても、進行を止めることも症状を改善することもなく、使用適用は軽度に限られます。一方で、脳浮腫や微小出血の副作用の危険もあります。アミロイドβが原因か結果かは不明です。
(7)誤嚥性肺炎は食べたものだけでなく、唾液の誤嚥でも起こり、胃ろうにしたから安全というわけではありません。
(8)さらに、入院して抗生剤投与や人工呼吸などの治療をしても、嚥下機能は回復しませんから、再発する可能性は少なくありません。
3.健康の出口
健康の呪縛から自由になったとき、それが健康の「出口」です。いつまでも健康を追い求めてもキリがありません。老化が原因で起こる病気のほとんどは、医療では治せません。下手に病院に行ったりすると見つけなくていい病気まで見つけられ、重症化して入院すると、次々新手の治療が繰り出されて、気がついたらチューブと機械だらけの悲惨な延命治療になっていることも稀ではありません。
よって、残された時間をどう使うか真剣に考えたら、健康に時間を取られるより、ほかにすべきことがいろいろあります。
まちがいだらけの「健康」願望。
健康を望みすぎず楽しく老いる。
2025年1月16日 9:04 カテゴリー:書籍紹介
書籍紹介「肝臓のはなし」竹原徹郎 著
「肝臓のはなし」
竹原徹郎 著 ISBN-978-4-12-102689-7
今回は前回に続いて、「肝臓の主な病気」を取り扱います。
Ⅱ 肝臓の主な病気
1.黄疸(赤血球のビリルビンの処理)
(1)120日ほどの寿命の赤血球は主に脾臓で破壊され、黄色の色素ビリルビンに変換されます。
(2)不溶性のビリルビンはアルブミンと結合し肝臓に運ばれ、肝臓は水溶液のビリルビン(抱合)にして胆管に流します。
(3)その後、水溶液のビリルビンは「胆汁」の一部として胆道を経て十二指腸から消化管に排泄されます。
(4)黄疸は赤血球の破壊が過剰になると生じたり(新生児黄疸)、肝臓の病気や胆汁が胆道から消化管に排泄されない場合にも生じます。
2.肝炎ウイルス
(1)肝炎ウイルスはA型、B型、C型、D型及びE型の5種類に分類されます(発見の順位はB型→A型→D型→E型→C型)。
(2)A型とE型は「流行性肝炎」の原因になるウイルスで急性肝炎を起こしますが、持続感染はありません。
(3)両型ともにウイルスに汚染された水や飲食を介して感染し、A型は魚介類、E型は食肉を介して感染することがあります。
(4)D型は特異なウイルスでB型に感染している状況においてのみ感染性ウイルスを作る「欠損ウイルス」です。
(5)B型とC型は「血清肝炎」の原因になるウイルスで、体液や血液を介して感染し、持続感染します。
(6)B型肝炎に対する薬剤はウイルスの複製を阻害する核酸アナログ製剤が用いられます。複製を抑制するだけなので、ずっと飲み続ける必要があります。
(7)C型肝炎に対する薬剤はウイルスの特定の分子の機能を抑制するDAAが使用されます。高額な薬剤ですが、2週間位の服用で完了します。
3.肝臓がん
(1)年間約5万人の方が肝臓の病気で亡くなりますが、劇症肝炎(急性肝不全)は数千人で、残りの大多数は慢性肝疾患です。
(2)慢性肝疾患の原因は肝炎ウイルス、脂肪肝、アルコール、自己免疫など様々ですが、プロセスは、肝臓の慢性炎症→硬化(線維化)→がん化という同一の流れになります。
(3)肝臓がんには「肝細胞がん」と「胆管細胞がん」の2種類がありますが、約9割は肝細胞がんです。
(4)肝臓がん診療の特徴は以下の3つです。
・腫瘍生検よりも画像診断が重視される(超音波検査→造影剤を用いたCTやMRI)。
・治療法の選択には肝臓の残存予備能力が問題になります。
・慢性肝疾患から発生するので再発が多い(異所性発がん・異時性発がん)。
(5)治療法は早期であれば、ラジオ波焼灼治療あるいは外科的切除、中程度であれば肝動脈化学塞栓療法、重度であれば様々な抗がん剤治療が行われます。
4.肝硬変
(1)肝臓が線維に置き換わることにより肝硬変が生じ、肝臓の機能が損なわれる「肝不全」に到ります。
(2)また、線維化し、肝臓が硬くなると、門脈からの血流が堰き止められ「門脈圧亢進症」が発生します。
(3)肝臓はあまりにも機能が複雑なために、人工臓器は実用化されていません。従って、肝不全になると他者からの肝移植することが究極治療になります。
(4)肝移植では、免疫抑制治療などが必要になりますが、移植後6ヶ月以内に約20%で発生する合併症を乗り越えると、その後は長期にわたって元気に暮らせます。
(5)門脈圧亢進症になると、側副血行路(シャント)ができて、肝臓を介さずに血流が心臓に還っていきます。
(6)すると、食道静脈瘤や胃静脈瘤ができ、それらが破裂すると大出血を起こし吐血や下血をし、命にかかわることになります。
(7)側副血行路が形成されると門脈に流入する血液が全身に入り、感染症が起こりやすくなったり、肝臓が萎縮したりします。
(8)また、アンモニアを含んだ血液が直接心臓に入り、頭にめぐると「肝性脳症」が起こりやすくなります。
(9)さらに、腸管から吸収されたグルコースも肝臓を素通りし、血糖のコントロールも不良になります。
2024年12月19日 9:02 カテゴリー:書籍紹介